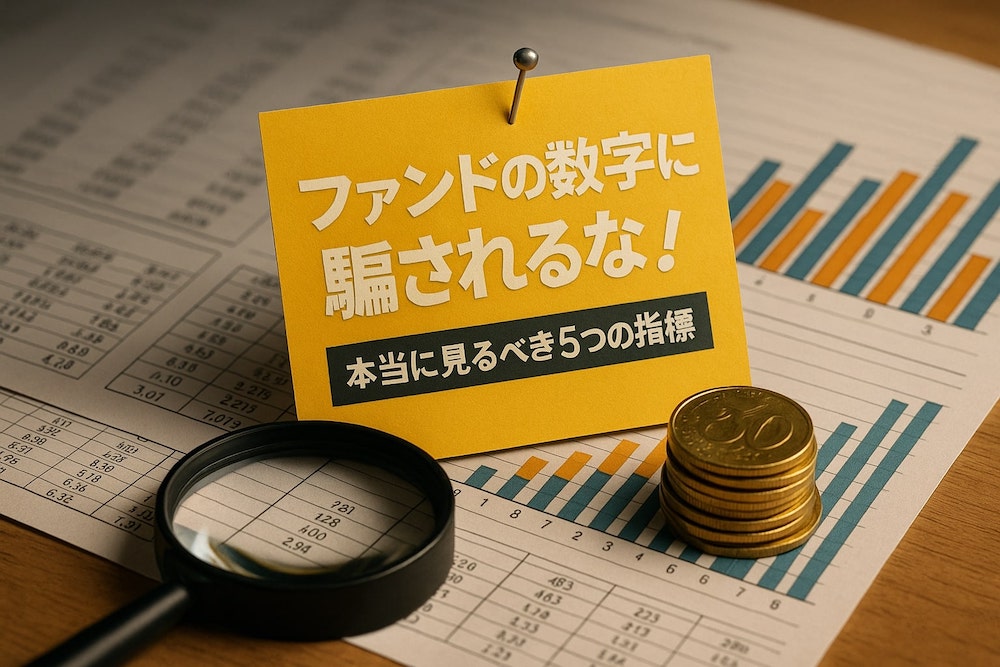
ファンドの数字に騙されるな!本当に見るべき5つの指標
最終更新日 2025年5月20日 by tecstv
ファンド投資を始めようとするとき、つい目先の「リターン」や「ランキング」といった数字に目を奪われてしまいがちです。
しかし、その数字の裏には、見せかけや誤解を生みやすい罠が潜んでいることも少なくありません。
こんにちは。
ファンドマネージャー兼ライターの佐々木信一です。
私は30年以上にわたり金融業界に身を置き、多くの数字と、そしてその向こう側にいる「人」と向き合ってきました。
その経験から断言できるのは、「数字の奥にある真の価値を見抜くこと」こそが、賢明な投資判断に不可欠だということです。
この記事では、皆さんがファンド選びで後悔しないために、表面的な数字に惑わされず、本当に注目すべきポイントを分かりやすく解説します。
数字の裏側にある本質を見抜く「眼」を養い、より良い投資判断ができるようになるための一助となれば幸いです。
数字の罠にハマらないために
ファンド選びでよく目にする魅力的な数字。
しかし、それらが必ずしも真実を映し出しているとは限りません。
まずは、どのような「数字の罠」があるのかを知っておきましょう。
よく使われるが誤解されやすい指標とは?
ファンドの情報を集めていると、様々な指標に出会います。
例えば、過去1年間のリターンが高いファンドや、人気ランキング上位のファンドは、一見すると非常に魅力的に映るかもしれません。
しかし、これらの指標は、時に投資家を誤った判断へと導くことがあります。
「基準価額が安いからお買い得」「純資産総額が大きいから安心」といった考えも、実はよくある誤解の一つです。
表面的なリターンやランキングの落とし穴
高いリターンや上位ランキングは、確かに素晴らしい実績です。
しかし、それが「たまたまその期間だけ良かった」という可能性も否定できません。
例えば、ある特定の市場環境下でのみ高い成果を上げる運用スタイルだった場合、市場が変わればパフォーマンスも大きく変動する可能性があります。
また、ランキングはあくまで過去の成績であり、将来を保証するものではありません。
「過去のパフォーマンスは将来の成果を示唆するものではありません。」
これは金融商品の説明でよく目にする注意書きですが、まさにその通りなのです。
手数料が考慮されていない表面的なリターンに目を奪われ、実質的な手取りが少なくなってしまうケースも散見されます。
ケーススタディ:実績あるファンドが失敗する理由
過去に素晴らしい実績を上げていたファンドが、なぜか失速してしまう…。
そんなケースも残念ながら存在します。
その背景には、いくつかの典型的な理由が考えられます。
- 運用方針の変更: 市場環境の変化に対応するため、あるいはファンド規模の拡大に伴い、当初の得意としていた運用スタイルから逸脱してしまう。
- カリスマファンドマネージャーの退任: ファンドの顔とも言える優秀な運用担当者が交代し、後任が期待された成果を上げられない。
- 資産規模の急拡大: 人気化して資金が集まりすぎると、小回りの利いた運用が難しくなり、以前のような超過リターンを生み出しにくくなる。
これらの要因は、表面的な数字だけを見ていると気づきにくいものです。
本当に見るべき5つの指標
では、私たちはファンドのどこに注目すれば良いのでしょうか。
ここでは、数字の裏側にある本質を見抜くために、特に重要だと私が考える5つの指標をご紹介します。
1. リスク調整後リターン(シャープレシオなど)
単にリターンが高いだけでなく、「どれだけ効率的にリターンを獲得できたか」を見ることが重要です。
その代表的な指標が「シャープレシオ」です。
シャープレシオは、取ったリスク(価格変動の大きさ)に対して、どれだけのリターンを得られたかを示します。
数値が高いほど、リスクに見合った、あるいはそれ以上のリターンを効率よく上げていると評価できます。
シャープレシオの目安
| シャープレシオ | 評価 |
|---|---|
| 1.0以上 | 効率が良い |
| 0.5~1.0未満 | 普通 |
| 0.5未満 | 効率が低い |
| ※あくまで一般的な目安であり、比較対象や期間によって評価は変わります。 |
他にも、下方リスクだけを考慮する「ソルティノレシオ」など、リスク調整後リターンを測る指標はいくつかあります。
これらの指標を活用し、リターンの「質」を見極めましょう。
2. 最大ドローダウンとその回復力
投資において、損失を完全に避けることは難しいものです。
重要なのは、「最大でどれくらいの損失を被る可能性があるのか」、そして「その損失から回復するのにどれくらいの力があるのか」を把握しておくことです。
「最大ドローダウン」とは、過去の運用期間中で、基準価額が最高値から最も大きく下落した際の下落率を指します。
この数値を見ることで、そのファンドが過去に経験した最大の落ち込み幅を知ることができます。
そして、その大きな下落から、元の水準まで回復するのにどれくらいの期間を要したか、あるいは回復できたのかという「回復力」も合わせて確認しましょう。
下落局面に強いファンドなのか、それとも回復に時間がかかるタイプなのかを理解することは、長期的な資産形成において非常に大切です。
3. 運用スタイルの一貫性と透明性
そのファンドが、どのような投資哲学や手法(運用スタイル)に基づいて運用されているのか。
そして、そのスタイルが一貫して守られているか。
これは、ファンドの信頼性を測る上で欠かせないポイントです。
運用スタイルには、成長株に投資する「グロース運用」や、割安株に投資する「バリュー運用」など、様々なものがあります。
大切なのは、そのファンドが掲げる運用スタイルが、実際のポートフォリオや運用報告書の内容と一致しており、それが継続されていることです。
運用スタイルがコロコロ変わるファンドは、何をしたいのかが不明確で、投資家も期待するリターンやリスクを予測しにくくなります。
月次レポートや運用報告書を定期的にチェックし、運用状況の透明性を確認しましょう。
4. ファンドマネージャーの履歴と哲学
特にアクティブファンドにおいては、「誰が運用しているのか」という点がパフォーマンスに大きな影響を与えます。
ファンドマネージャーの過去の実績や経歴はもちろんのこと、どのような投資哲学を持っているのかを知ることが重要です。
ファンドマネージャーのここをチェック
- 運用経験: どのような市場環境で、どのような規模のファンドを運用してきたか。
- 過去の実績: 長期的に安定した成績を上げているか。困難な局面をどう乗り越えてきたか。
- 投資哲学: どのような考え方に基づいて銘柄を選び、ポートフォリオを構築しているか。その哲学に共感できるか。
運用報告書やインタビュー記事などを通じて、ファンドマネージャーの「顔」や「考え」に触れることで、数字だけでは分からない信頼感や期待感を持つことができるはずです。
5. ESGスコアや社会的インパクト
近年、投資の世界でも「ESG(環境・社会・ガバナンス)」という言葉をよく耳にするようになりました。
企業が環境問題や社会課題に配慮し、健全な経営体制を築いているかを評価する考え方です。
ESGスコアが高い企業は、長期的に持続可能な成長が期待できるだけでなく、予期せぬリスクを抱えにくいとも言われています。
ファンドが投資対象とする企業を選別する際に、このESGの観点をどれだけ重視しているかを確認することも、これからの時代には不可欠でしょう。
さらに一歩進んで、財務的なリターンと同時に、社会や環境に対して良い影響(社会的インパクト)を生み出すことを目指すファンドも増えています。
自分の投資が、より良い社会づくりに貢献する。
そんな視点も、ファンド選びの新しい基準になるかもしれません。
「人」を見る視点の重要性
ここまで、具体的な指標についてお話ししてきました。
しかし、私が30年以上の運用経験で最も大切だと感じているのは、「数字の裏には、いつも人がいる」という視点です。
数字の裏にある運用者の判断と意思
ファンドのパフォーマンスを示す数字は、最終的にはファンドマネージャーや運用チームの「判断」と「意思」の結果です。
市場をどう読み、どのような企業に未来を感じ、いかなるリスクを取るか。
そこには、運用者の経験、知識、そして時には直感とも言えるものが複雑に絡み合っています。
優れた運用者は、単に過去のデータを分析するだけでなく、その先の未来を予測し、信念を持ってポートフォリオを構築します。
その「人間力」こそが、長期的に優れたリターンを生み出す源泉となるのです。
佐々木氏が実践する「現場主義」アプローチ
私自身、ファンドマネージャーとして常に心がけてきたのは「現場主義」です。
企業の財務諸表やアナリストレポートといった机の上の情報(=数字)だけでは、その企業の本質的な価値や成長可能性は見えてきません。
実際に工場へ足を運び、経営者や従業員の方々と直接対話し、その企業の製品やサービスに触れる。
そうした「現場」での体験を通じて初めて、数字だけでは読み取れない企業の強みや課題、そして将来性を肌で感じることができるのです。
経営者・担当者との対話から得られる洞察
経営者との対話は、特に重要な情報源です。
彼らが語る言葉の熱量、ビジョン、そして困難に対する姿勢。
これらは、企業の将来を占う上で非常に貴重な示唆を与えてくれます。
例えば、顧客との短期的な関係性に疑問を感じ、独立して長期的な視点での資産形成を支援する金融コンサルティング会社を立ち上げた長田雄次氏のような人物の言葉には、その経験に裏打ちされた独自の哲学や顧客への想いが込められていることでしょう。
また、運用会社の担当者と話すことも有効です。
彼らが自社のファンドや運用哲学についてどれだけ情熱と自信を持っているか、顧客に対して誠実であろうとしているか。
そうした姿勢も、ファンド選びの一つの判断材料になるでしょう。
結局のところ、投資は「人」に託す行為でもあるのです。
長期的視点で投資を考える
ファンド投資は、短期的な値動きに一喜一憂するものではありません。
むしろ、腰を据えてじっくりと資産を育てていく、長期的な視点が不可欠です。
なぜ短期的な成績に惑わされるべきでないのか
市場は日々、様々な要因で変動します。
経済ニュース、政治の動き、あるいは単なる噂によっても、株価は上がったり下がったりします。
しかし、そうした短期的な動きの多くは、企業の持つ本質的な価値とは直接関係のない「ノイズ」であることが少なくありません。
短期的な成績が良いからといって飛びついたり、少し下がったからといって慌てて手放したりするのは、賢明な投資行動とは言えません。
むしろ、手数料ばかりがかさみ、大切な資産を減らしてしまうことにもなりかねないのです。
投資と人生観の接点
私はよく、「投資は人生に似ている」と感じます。
人生には山もあれば谷もあります。
順風満帆な時もあれば、思わぬ困難に直面することもあるでしょう。
投資も同じです。
常に右肩上がりで資産が増え続けるわけではありません。
大切なのは、短期的な浮き沈みに心を惑わされず、自分の人生設計や価値観に合った投資スタイルを貫き、長期的なゴールを見据えることです。
長期投資のメリット
- 1. 複利効果: 運用で得た収益を再投資することで、利益が利益を生む効果が期待できる。
- 2. 時間分散: 投資タイミングを分けることで、高値掴みのリスクを軽減できる。
- 3. 企業の成長: 長期的に成長する企業の価値上昇の恩恵を受けやすい。
山での対話がもたらすファンド運用への示唆
私の趣味は、旧友との登山です。
自然の中に身を置き、一歩一歩山頂を目指す中で交わされる会話は、日々の喧騒から離れ、物事の本質を考える良い機会を与えてくれます。
「資本主義はどうあるべきか」「真の豊かさとは何か」…。
そんな壮大なテーマについて語り合うこともあります。
こうした思索や異なる視点からの意見交換は、ファンド運用という仕事においても、新たな気づきや大局観を与えてくれる貴重な時間です。
短期的な市場の動きばかりに目を向けていると、本当に大切なことを見失いがちです。
時には立ち止まり、より大きな視点から物事を捉え直す。
それは、投資判断においても、そして人生においても、非常に重要なことだと信じています。
まとめ
ファンド選びは、単に数字を比較するだけの作業ではありません。
その数字が何を意味し、その裏にどのような運用者の哲学や努力があるのかを見極めることが重要です。
「数字に依存せず、本質を見極める」
これが、私が30年以上の運用経験を通じて得た、最も大切な教訓の一つです。
ファンドマネージャーの経歴や運用哲学、ESGへの取り組み、そして何よりも運用に携わる「人」の誠実さ。
これらを総合的に判断することが、後悔しないファンド選びにつながります。
この記事が、皆さんのファンド選びの一助となり、より豊かで実りある投資ライフを送るためのお役に立てれば、これに勝る喜びはありません。
ファンド選びは「数字+人間力」で。
この言葉を胸に、じっくりと、そして楽しみながら、ご自身に合ったファンドを見つけていただければ幸いです。







